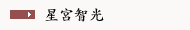(一)はしがき
不躾(ぶしつけ)な云い方だが修験とか山伏とか申しますと、採燈を焚いたり火生をやったり山登りをする一団で病気を拝んだり、おまじないや占いを渡世に暮らす怪しげなお天狗宗旨位いにしか扱ってくれないような感じもする。 戦時中私が或る佛聯支部の幹部会に出席した時、一向宗の坊さんが法印(修験)と云う奴は坊主か俗人かそれとも神主か会体のわからぬものだと云って義務金拒否に絡んで非難攻撃をしたのを目の当たり聞きまして今更ながら衝撃を受けたことでありました。勿論気にする要はないと云えばそれまでだが明治初年頃のお上のお布令を見ましても舊(きゅう)修験者の病人祈祷などに対するきついお達示が度々あったことなど思い合わせ官からも民からも低級扱いにされていたことは事実であったとしか考えられぬ。 然るに宗教法人令が施行されて以来独立を叫んで雨後の筍と申しては大袈裟だが兎に角修験と銘打った看板が十を以て数うるに至った、まことに隆んなりと云うべき乎(や)。この現象を見まして一般宗教界は奇異な観を抱いたのも無理からぬことで、てんで問題にしなかった行者道が、斯様に争って分派独立したと云うことは、それ自体何物かを物語る理由がなければなるまいとする好奇心に駆られた疑問を生むに至ったと云うことは修験道の歴史や内容を知る者にとって当然点頭づける事柄なのであります。 永い歴史と変遷と発展を辿って来た斯道(このみち)は全国に漲(みなぎる)民衆的広大性をもった自由な信仰形態が一面は醇化されて充実した果実を結んだが、他面には尚を複雑多岐な不純な内容や単純な要素も含まれて居るために不統制に禍されて、缺陷(けっかん)を曝露するに至ったのでありまして、衰微破綻その極みに達した観があるのであります。 斯様な訳で、それに認識不足も手伝って世間から斯道の真價も認められず剰え似而非山伏が横行し八卦卜筮を本業とする行者輩の續出を來し修験の真髄を會得するもの次第に姿を消すに至ったと云うことは、獨り行者道のみならず宗教を軽んずる世相と相俟って仏教界全体に渉る現象ではありますけれども、お互いに一大猛省を要するものあるは勿論でありましょう。 (つづく)
[宗報第六号昭和二十三年十一月二十日発行掲載] [宗報二一九号平成十年一月一日発行再掲載]
(二)修験道の発生、経路、発展、並びに将来について
前に申しました通り修験道は長い歴史を辿りつつ複雑多岐な要素を混淆融和して発展したものであり、その内容性格、形態も各時代によって著しく異なる相貌を呈して居るのでありまして系統も種々あって一様ではないのであります。その淵源を尋ねますと民間に行われた禁厭、筮術、亀卜、夢告、神託のやうなものから発生して奉幣、巡禮の風習と結びつき、山嶽崇拜と関連し日本神祇の信仰を目標として支那の道教とも習合し霊験の発顕、吉凶禍福や除災招福、療病的祈祷術も織り込まれ民間に伝った雑密なども早くから流れ込んで、これらの影響も少なからず受けたようであります。従来の土俗的神祇観念に根ざし、これを母体としてこれと関連する習俗もからみ合い仏教の入来と共にこれと習合、合体して出来上がったものであると云うのが歴史家の一致した説のようであります。 発生的な方面から見ますと修験道の起源はかかる民衆一群の信仰者の系統の中に求められ宗教としての道統も亦かかる源流に発して居るのであります。 殊に農耕と雨水の関係から山岳が崇められ山川の奉幣と云うことが古くから行われ仏教渡来と共に祈雨のために金光明経、仁王経、大般若経、孔雀経などが読誦せられて宗教上の行事となり霊岳への登拝、山林徑行が国民的信仰行事の一つの傾向となり、時代の経過と共に印度古来の修道形式たる頭陀の行法が用いられ修行と云う宗教形式が生まれ出づることになったようであります。ともかく、公式に仏教が日本に入る以前から神道、儒道、仏道の三道が混淆(こんこう)した形式で発展しつつあったことは容易に窺われるのであります。 官途を通じて正式に渡来した仏教が官符の宗教として制度化し貴族化する反面、従来民衆間に行われた斯様な土俗の信仰、殊に卑近な実用的な信仰、例えば禁厭祈祷や神占的な民間信仰が別な道統を辿り佛教の要素を取り入れつつ民間の間に喰い込んで行ったのでありまて、優婆塞行者としての役小角が此の方面に現れた最初の権威者であられたことは申すまでもありません。然し行者の渡天後傳承者は益々殖えては來たが民間行者から頭角を現はす者がなかったと共に顯密兩門の發達隆昌を極むるにつれ、又官僧たる圓珍、聖寳の二大師が役君の遺蹤を踏むにつれ感應得驗の行蹟に酬いて佛教の色彩濃厚となり佛教風の修行へ移行し、三井の法流を汲む増譽、行尊、覺宗、覺讃、覺忠、房覺の高僧等の出ずるに及び相次いで熊野三山検校となり本山修驗の隆昌を來し、又醍醐三寳院の滿濟准后以後東密小野流の流れを汲む高僧等大峰検校を號するに至り共に全國の民間行者輩を統轄し、この二つの流れが本山、當山の二派に分かれ修驗道の主流となって特殊な道風を形成するに至ったのであります。この二派が後世、峯中法流、慧印法流として發達を遂げたのであります。前者は天台系統であり後者は眞言系統であることは申すまでもありません。 學匠相次いで起こり教學上特異の發達を遂げた九州の彦山修驗は峯中法流に属しますが別途に發展を遂げたものに出羽の羽黒修驗、日光に日光修驗、回峯修行を主とした山門の北嶺修驗、徳一上人の流れを汲んだ筑波修驗、婆羅門僧正の傳流、此外伯耆の大山修驗の一團、加賀の白山修驗の一團、又靈家神道を創めた戸隠山の修驗宗團もあった。 室町時代から徳川時代にかけて死者の葬式法要が寺院外には許されなかった制度が出來てからは病氣や災難に關する祈祷方面即ち現世利益を追求するには自然民間行者の手にゆだねられるようになったのであるが、山岳登拜や神社参拜の先達を勤めて居った山伏行者に混じ神主が登場し神道の色彩を濃厚にした修驗の一派が現れて來たのであります。その主なるものは御嶽講でありましょう。もともと修驗道の始まりは神祇の信仰に根ざして居るのでありますから時代の變遷につれて還元するのも自然であったろうし神佛混淆の宗門として展開して來た以上當然でもあったでしょう。 御嶽講の元祖は尾張の覺明行者、次いで武藏の普寛行者、一山行者、越後の一心行者等相次いで現れ御嶽教に属する御嶽講社の一團を形成するに至ったのであります。其の他扶桑教に属する富士講、寛行教に属する不二講、元の神宮教に属する伊勢講、大社教に属する敬神講、禊(みそぎ)教に属する登保加美講、出羽三山に属する敬愛教會など擧げればもっとありましょう。又黒住教、金光教、天理教など宗派神道にして修驗行者との因縁關係から出發して發生した教派もあるのであります。 法人令發布後、修驗の名称を掲げ斯道の行法を目的として獨立した宗派も數あるが、所謂修驗道として今日行法としても教義としても特殊の發達を遂げ民衆的宗教として教界に異彩を放って居るものは三井寺の開祖智證大師の流れを汲むものと醍醐寺の開祖理源大師の流れを汲むもの即ち元の本山、當山の二大法流であり又宗團は小さいが照見大菩薩(崇峻天皇の皇子蜂子王子)を開祖とする羽黒修驗道(修驗本宗)が特色あるものと謂えましょう。 然し乍ら、修験道の性格から申しましても世界觀、人生觀から申しましても時代に即應し將來他のあらゆる宗教と混淆する可能性が充分あるのであって民衆的宗教たる特性の存する所以はここにあると共に既成の修験宗團がそのままの性格を以っては必ずしも將來性あるものとは斷言出來ないところに又興味もあると思われるのであります。 由來修験道なるものは一定の時期に一定の人によって作られたものではなく、時と人との経過に伴い徐々と組織立てられたものであり、民間に起こった種々な行事が行法として理論付けられて教義も発達し行法も発達してきたものであるから永久一定の教義に縛られて動きのとれぬ不自由のものでは勿論ないから他の宗教とも何時でも握手の出来るものであり何時でも変貌し得るものであります。実はそこに弱点もあろうしまた特徴もあろうと云うもので謂はば興味津々たるものありと云わねばなりません。 神道にせよ佛教にせよ、我が国の既成宗團が何れも行き詰まりを來し活路を求むべく余儀なくされて居る現状に於いて、修験の宗團も菖套を脱し更に躍進せねばならぬ運命に直面して居ると思うのでありますが、要は人物の問題であってその宗門が盛んになるのも反対に衰うるのも結局は人間の如何に帰着するのであって、抜群の人物の下に多くの帰依者が集まって宗門は栄えて行くのであるから早く目覚めたる者こそ、別な言葉で申せば時代を認識し時代精神を正しくキャッチした者こそ教界の次のバトンを握ることになるのでありませう。 修験道は本来教理や聖典に捉われぬところに将来への示唆に富む性格をもっておるのでありまして、それは斯道の教義の根本内容を見れば一目瞭然たるものがあります。二、三抜粋してみますと、 『當道の依経とは法爾常恒の経是なり』 斯様な表現で根本立場を説明して居るのであります。然し乍ら修驗道は大自然界を道場とし師範として居りますが、眞言宗の様な高踏的な密儀を排して実修実行を旨とはしたが稍もすれば実生活から遊離せんとする傾向に堕し又倫理的要素にも欠けて居るところもあり、魅力はあるが余りに広大な莫たる構想に陥り剰え感化の源泉力に欠けた憾みもあり大いに反省せらるべき点もあるのであります。でありますから修驗道が生かさるるも殺さるるも人に因ることとなるのであって、これは宗教一般に就いても左様言わるべきでありませうが特に斯道に就いて然る所以が痛感せらるるのであります。 修驗道の行法の根底は申すまでもなく密教の思想を基調とした神秘的汎神論の上に立って居るが、禅や浄土教の流れや華厳や法華の思想も多分に入り込んで居ると共に現身成仏を理想としながら尚且つ未来の守護と保證を求めた成仏を願って居ると云った具合で、甚だ不統一な感はあるが敢えて矛盾もなく自由に発達してきたところに特徴があるとも云われませう。然し修驗道の一大損失として挙げられるべき問題は獨り大峯山のみならず各地の国峯も慣習的に女性を容るる余地のなかったことで現在並に将来これは致命的な打撃となるのであって、今後大に打開策を講ぜねばならぬ問題でありませう。 (つづく)
[宗報第七号昭和二十四年一月一日発行掲載] [宗報二二〇号平成十年四月一日発行再掲載]
(三)修験道とはどんな宗教か(その一)
修験道が仏教風の修行の中に移行したとは云え、元来民族信仰に根ざして発足したのでありますし一般国民の宗教が神棚を祀り仏壇を設けて敬神崇仏と云う神仏一如の信仰形式で今日に至ったのでありますから、自然民衆教たる修験道はこれに即応し神仏不二の教理を展開し推進して今日に至ったのであります。そこに他宗と異なった特色はあるが密教の盛んになるにつれその色彩も濃厚となり混沌とはなったが、齟齬(そご)を来すこともなく一般民衆の先達となり国利民福をモットーとして一意霊験の発得実現という方向に向かって歩みつつ今日に至ったと云ってよいでせう。 然し今日のやうな科学万能の世の中に遭遇して従来の伝統的観念や構想的儀式そのままに捉われて心構えを新たにせずんば、果たしてよく信仰を保ち得るかどうか、これは獨り修験道のみならず一般教界に課せられた問題でありますが、科学奥にひそむ真理に向かって時代に適応したる済度教化の威力を発揮し打開の斧を揮う責務こそ重大なりと思われるのであります。 行場霊地たる山嶽を遍歴修練して咒験の證得を目指す修行は平安の末期から一世を風靡したようであって山伏、験者(けんざ)と云う名称の起こったのは可成り古いが修験道と云う名称の出来たのは比較的遅れており「靈異記」の記述には、この意味合いの文字が読みとれるが「修驗名称原義」などを見ても何人が何時唱道したか正確には明らかではないようだ。修持得験とか修咒得験とか持験、咒験という風に用いられ又修道とか験道とか験乗とか云い習わされて何時とはなしに修験道となったもののやうである。道と宗の名称に就いても優劣適否の解説はあるが古くは道を採り宗を嫌ったのであります。 修験道の基調は全体として密教的であるが思想や教相談義よりは寧ろ実修実證を眼目として発展したのでありまして、綾錦を身に纏い練り歩く趣味の生活を送るためでもなく、高座に登って高遠な理想を説くためでもなく、優美上品な生活に楽しむためでもなく、或いは現世を厭い山林に隠遁して行いすます入道生活を欲するためでもなかった。真剣に現実生活を営むために外ならなかったのであって如何にして苦悩を克服し力強く生き抜くか、それが命題であったのであります。儒道にも神道にも仏道にも喰い入ったのは、それらを日常生活の糧として窮塞を打開し、真理生活に織り込み、心に光明を保ち生活に幸福を実現し肉体も健康化して行くため、つまり現當二世に渡って悉地を得やうと云ふ目的からで、一宗一派の教義に拘泥しなかった理由もそこにあったと思われる。堂上に安座する単なる観法や修法に止まらず躬自ら大自然界に融け込み、そこを道場としてこんなん艱難にぶつ突かり地獄や餓鬼の苦痛を乗り超えて勇健剛邁の修行に精進したと云うことは要するに三大阿僧祇却を一念に超ゆる一超直入の効果を収めるためで、それは心の中から一切の曇りを吐き出す、一切の執着を放下する、つまり一口に云えば観念の洗浄をやるためであって出家在家を諭せず剃髪有髪の外儀を問わず肉食妻帯の有無に拘わらず貴賤を通じて、その功徳に浴することが出来る山伏道の本領であって現身に法如を證する此岸的な現世的宗教たるところに特徴があると思われるのであります。 さて「修験道とはどんな宗教か」を語るに當り人間の本体は心であって物質ではないと云うことから筆を進めてみたいと存じます。般若心経を精読しますならばこの道理はよくわかりますが肉体は本来心の影であって本當の健康は「久遠の健康」を掴んだときに自覚できるのであります。移り変わる日々の肉体の健康が本當の健康ではなく肉体は無常であって日に日に変わるのであり昨日の細胞は今日の細胞ではない、自分が佛の子である神の子であるという自覚こそ久遠健康の自覚でありませう。 人間は宇宙の渾一的生命、大調和の統体たる大日如来(神と云ってもよい)を離れた存在でなく元々同体たることを自覚せねばなりません。形の世界は「観念の映像の世界」であって人間を物質的機械だと観ずる唯物史観的な考え方は迷信であって、現代の吾々は人間の本據たる牙城に突進して霊光によって洗礼を受ける必要ありと存じます。吾々が何か事物に「心」が引っかかると云うのは感覚に見える現像世界の事物を実在だと思っているから、それに執着し、執着するからそこに心が捉えられる。感覚で見る世界の事物は実在ではなくて影である。影だと知ったら執着する必要が無くなる。執着しなかったら心が何處にも引っかからない、引っかからなかったら心は本来の自由を得る。この辺の道理は古来修験者が祈祷のために日常読んだ『般若理趣分』に巧みに要約して説かれてあります通り五官で世界を眺むればそれは物質でありましょう。然し実相覚で見れば妙々不可思議なる霊質で此世は出来ている。在りとし在らゆるものを在らしめてをる一つの力、生とし生けるものを生かしめてをる一つの力それを神と称し大日如来と唱えるのであってこれが真の生命であって完全の別命であります。 世尊一代所説の五千余巻の蔵経も至極は法華一部八巻の中に促り法華一部六万九千三百八十四字の極意は妙法蓮華経の五字に促り、五字は妙法の二字に促り二字は心の一字に帰す。妙法の一心展れば十方法界を含有し収むれば無念無心の自性に帰す。此故に心外無法、三界一心、諸法実相と説かれてある。法華経と云い、無量寿佛と云い本来の面目と云い、阿字不生と云い、根本無作の戒体と云い、無相三密と云い或いは高天原と云う皆一心の異名だと説かれてあります。三世諸佛番々出世の本懐は『一切衆生開佛知見』のためであり一心の妙法たることを見出すにある。佛法は『心地の法門』で心を離れて成り立たぬ。一切経は要するに心の註脚であると古人は云うてをります。不景気が先に起こるのではありません、心に起こった不景気が次に形を現したのでありまして経済界も心のままになるのであります。 歳毎に咲くや吉野の山桜 修験道は実験宗だと力んでも心を離れて何の実践ぞやで、大日経の所謂『実の如く自心を知る』ことが修驗の大綱でありませう。『大峰山は何処に在る?』と問う人あらばポンと胸をたたいて見せる底の教養は欲しいものであります。天地の至道というものは実は近きところにある。日々語る言葉そのものが至道の露現であると共に山も川も日月も森羅万象皆無限絶対の露現であり生死共に至道の當作であり宇宙生命の活躍そのものである。『往生』とは往いて生まれる事です。修験道では死んで無くなると云う相談は致しません。活路を見出して開く相談ばかりするのです。人生の現実生活に於ける自己を万徳円満化せんとする努力を持続して法界の軌道に乗ろうとするところに修行の目的はあるのです。 法は絶対であって一所一物に固着しません。人情自然の発露も亦法であり、そこを徹見観得するにありませう。『平常心是道』というのはそこでせう。日常の行住座臥、即ち吾人の現実生活の當体たる自己心是れ平常心であって取りも直さずこれ道である。この心と現実生活とが協調活動するところ是れ即ち道の露現であります。修験道が実行宗だと云うのはそこを云うのです−。成佛とは覚つた心的状態であって自己の認識批判、味得、体験の中にあって自己以外にはない。人生そのものの當体をあるがままに正しく究竟したものであれば、それは法を見たのでありませう。法は一切現象、一切生活上に如々さながら到るところに、いつでも動き働いて寸時も停まることなき力であります。見ると見ざるとに拘わらず働く力ではあるが法は見るものに於いてのみ体得摂取せらるるのであります。故に法は之を見る者を通して作用が現れる、即ち具体化せられるのであります。『人法一如』と云うのがこれであります。『法を見たるもの』それは釈迦やキリスト、高祖、祖師、先徳等で、此の意味に於いて人法一如即法の人問的顕現であると申してよいでせう。修験道の狙いも要するにそこにあると思います。 広大無辺な宇宙は吾々を含めて一つの大きな生命体であります。森羅万象の當体そのものは宇宙の真理そのものであります。草木国土悉皆成佛とはそこを云ったものでありませう。 佛とは天地万物を引くるめての宇宙の生命体を指称した名であります。万物は何れも皆満足状態の境地を目指して進行しているのでありまして佛を念じその佛の目的を覚り其進行に身を委ねることが大切でありませう。人間の心には人生のあらゆる苦難を凌ぎ無限に向上せしめて行く力のあることは確かです。 無限の宇宙生命と有限の人間生命と同一なることを認識し有限生死の精神肉体も永劫不滅なる宇宙生命の現れなりと知る、人間生死の肉体がそのまま永劫不滅の生命を運び行く一丁場であることを悟る、悟るが故に安心立命して苦悶を除いた生活が出来る、信心とはこれを云うのでありませう。『當相即道即事而眞』と云うのもこの辺のことを云ったものであり我即アビラウンケンと云い、本不生位と云い、大日の覚体と云うのも、そこを云づたものでせう。四苦八苦にさいなまれる人生であればある程、冷静に其の原因、性質を見究め不動明王のやうに勇敢に之を取り除く手段なり生活方法なりを見出して向上一路を開拓して行く、苦労に蝕まれず苦労を有り難く頂戴して其處に人生の意義を観取る、人生の姿を多く広く深く観音様のやうに自由自在に観察し経験して行く、この体験こそ有り難いものではないでせうか。修験道が体験の宗教としての一つの特色はそこにあるのだと思います。迷わず溺れず自由自在に応機到達の要道を悟得し実行しつつ生活する、『手を挙げ足を動かす皆是れ大日の密印』の境地に到達するのが修験者の要諦でなくてはなりません。地獄、餓鬼、畜生、入るところとして主たらざる無き悠々たる三界の主の境地であります。 (つづく)
[宗報第八号 昭和二十四年五月一日発行掲載] [宗報二二一号 平成十年七月十三日発行再掲載]
(三)修験道とはどんな宗教か(その二)
さて然らば心の糧は何であるか。それは慈悲であって別な言葉で云えば愛である。救いの道も覚りの強さと愛の深さの内にある。観自在菩薩の大自在境、即ち神とか佛とか云う世界に近づくには佛性を開発せねばならぬ。内心に潜んでおる佛性を開発するには三宝帰依ということ、和合ということ、愛の結合ということ、神道式に云えば産霊(むすび)ということが肝心である。 慈悲や愛の言葉(真言)が名号となり加持力となり祈祷となり実行となって驚くべき創造力を発揮するのでありますが、病気が癒えるのも心願が達成出来るのも神通力を現すのも慈悲心に徹した信念の力であって、宇宙の一切事はリズム(波動)で出来ておりますからエーテル波動でも思念波動でも偉力を現すのであります。修験道の結袈裟や貝の緒は和合の真理を表示した人類愛の象徴でありますが、宇宙そのものが生命体であり生命の法則が備わっておる限り、そこに住む人生にも道がなければなりません。道は即ち生活であって、その生活が他人に及ぼす時、隣人愛となって行かねばならぬ。若しも顛倒妄想による思念、排他憎悪による感情によって生活道が押し進められる時は、自分の生命を妨げ同時に他人の生命を妨げることになるのであります。佛性を開発することによって妄想は除かれ貧瞋癡三毒転じて智慈勇の三徳現れ、生命の創化力は自ら発現するのでありまして、三宝帰依とは天地一切のものと和合し融合することであります。 神佛の前に法楽を捧げることは天地一切に感謝を捧ぐることであり何人にも感謝を捧ぐることなのであります。自分自身が現世にいきて居るということ、つまり此の世に生命を享て来たという事実は否定することは出来ません。自分の生きて居ると云う事実は取りも直さず自分自身が生命であると云うことである、自分自身が尊い生命であるという自覚がすべての道徳生活の根本でなくてはならぬ。自分自身が尊い生命であればこそ自分自身を恥かしめぬ生活をせねばならぬし亦他人の生命生活を尊重せねばならぬことにもなるのであります。延いては吾々の生命の大元たる大生命即ち大日如来をも尊重礼拝せねばならないのであります。これと反対に自分自身が尊いものであることが解らねば自分と同じ一個の生命たる他人を尊ぶべき所以も亦その本源たる神佛を尊ぶべき所以も解らなくなるのであります。 峯中法流に伝えられる柱源神法という秘法は厳かなる此の生命の本源を修行する行法でありまして、吾々が生命として現世に顕現して来た事実に即して自分を鞭撻し反省し浄化して生々化育し、生命の本質を深く掘り下げ宇宙生命の支流として行きつつ終には此の大生命に合して一緒になる、つまり未来永劫に滔々たる大生命の中に融け込んで行こうとする行法であります。 次に亦言葉が大切なものであることを申しますならば、弘法大師の『聲字實相義』に「如来の説法は必ず文字による、内外の風気緩やかに発すれば必ず響くを名けて聲と云うなり、聲発して空しからず必ず物の名を現すを号して字というなり。名は必ず体を招く之を実相と名付く・・・・・・聲字には必ず実相を有し実相には必ず聲字を有す互いに能所なり」とあり、又古事記には「天地の初めの時大宇宙に成りませる初の名は天の御中主の御言(みこと)」とあります。神道で云う尊とは美言(みこと)で互に敬し合い愛し合ったところからお互に神の子であると云う自覚に基づいた名称であります。 人生は言葉によって清くもなり醜くもなり幸福にもなれば不幸にもなるのでありまして、言葉は心の現れでありますから、謂はば神と同体であり心を練磨するには誠に大切となるのであります。咒咀、嫉妬、憎悪の恐ろしい精神から起こる言語波動は心から心へと感応して人の心を掻き乱し人類を混乱せしめて不幸に陥入れるのであります。喧嘩も雷同も戦争も源は心と言葉から発生するのであります。身口意の三密一致と云うことは行者道に於いては実に大事なことであるのであります。 悩み苦しみの感情波動を防ぎ止めるには有り難い解脱の言葉を繰り返すことが大切で、愛や慈悲や平和な言葉の波動は悪の波動を断ち切り之を超越し或いは同化せしめずには置かぬのであります。神変講式にある「無想三密の法味を施して一陀羅尼の実行を示す」とは斯様な事実を指摘したものでありましょう。 智証大師は「如来は法を以て身となし比丘は慧を以て命となす」と仰せられましたが、法の内容は如何なるものかを達観しますならば、それは三つの方面がある。 人間は勿論のこと総ての事象と云うものは刹那と雖も変化し遷流して一刻も休まざる流動的現象であるということ、流れておることが総てであって流れしめる力の実在があるのではないと云うこと、流れて止まざる姿がそのまま真実唯一の姿であると云うこと、これが所謂無常観であります。 第二には生命の中心的存在がないと云うこと、死線を超えて尚生き継げる霊魂的な作用も亦固より無いと云うこと、即ち一つの事相に中心的、個性的、恒久的な存在がないと云うこと、これが無我観であります。 第三に遷流常なく中心的個性の実在なくして如何にして現象が成立するかと云う問題が残るのであります。それは多くの力、多くの要素が一つの機会に一つの配列形式によって合集成したものであって、現象は関係に過ぎないと観るのであります。一相一象は縁(関係)来たりて生じ縁去りて滅するのであって恰も雲水の如しと観るのであります。縁起を観る者は法を観る者なりで、これが縁起観であります。 多数多量の要素が種々関係組み合わせにより森羅万象を生起せしめる即ち力、要素の相互依存、合集成とに表象されたる力の関係であるから遷流止まず、個定性なき事相なるにも拘わらず常住不変の個的存在ありと見るのが認識不足で、これを無明と申します。此の認識不足に因る本能的盲目的欲求が所謂煩悩であります。 人間は必ず死するものでありますが此の煩悩のために無限に生きんとする盲目的欲求に捉われて生命を無限の如く誤認し偸安を喜ぶのであります。故に煩悩の内容は自己欺瞞であるのであります。それ故人生の悲泣、大苦は此の自己欺瞞が厳然たる事実の前に曝け出された時に起こるのであります。それ故に無常無我の上に事相を正見し見得するということ即ち、おのずからに、さながらに、あるがままに、まことにあるべくすがたに実相を認識するに止まらず、正智正見し体験して身に心に体顕せしむると云うことが大切となるのであって、これが修験道の体験的修道の目標なのであります。 法の体験であり法の体顕であるが故に法は其人によって無限に働くことになるのであります。無我に生きる故に平等心に生きるのであり、自己一身に捉われざるのみならず一切に捉われざる故に捨身修行であり、般若無所得行なるが故に何物かを得んとして行為するに非ず平等一子の愛に生きる不動明王の心であるのであります。 (つづく)
[宗報第九号 昭和二十四年七月一日発行掲載] [宗報第二二二号再掲載]
(三)修験道とはどんな宗教か(その三)
無我に生きる者は亦縁起に生きねばならぬ。無量力に対する感謝、一切人力に対する感恩、それらの力に対する慈念、へだてなく、えらぶことなく、執することなく、嫉むことなく、自然さながらに、黙々として顕加冥加に感謝しつつ生きるのであります。法界への回向であり供養であると云うことです。佛道報恩行とはこのことであります。又無常に生きると云うことは如法の生活そのものであって清浄無垢心に生きることであります。「白露のおのが姿をそのままに、紅葉におけば紅の露」の心境である。 雑阿含の中に「天子問ふ、聖者無執着と聞く、沙門は教化に執せざるや。佛云う、智者は愚者を黙視すること能わず、世間人を哀愍するは法の所応なるが故に」と。法の所応云々は道の自然なるが故にと云う意味で他人の苦を見て見ぬふりは出来ないと云う意であります。天道人を殺さずとはこのことで、ここが所謂菩薩道奉仕行となって六波羅蜜救済道の面目躍如たるべきところとなるのであって、先規に通達して達者たるべき先達として衆生済度の良方便たる四攝の法(布施、愛語、利行、同事)を心得ねばならんこととなるのであります。修験道で云う捨身修行、十界修行とは要するに無常に生き、無我に生き亦縁起に生きることだと云ってよかろうと思います。 在ると云うことと生きていると云うことは一つのことであります。在るものは総て生きている。存在とは生命の別名である。生命とは又佛の別名である。佛とは完全の別名である。即ち存在するものは総て生命であり佛であり完全でなくてはならぬ。勿論存在すると云うことは物質的な相で「現れている」ということではない。形が現れていることを「ここに物がある」と云い、形が現れなくなると、それは「無くなった」と云いますけれども、それは唯「迷いの客観化したもの」が映って、出たとか消えたとか云うことを知る五官の働きだけのことであって物質と云うものは佛典の各所に説かれていますように夢の如く虚妄不実のものに過ぎないのであります。 本当の人間は物質の人間ではない。それは円相の人間、光明身の人間、自在身の人間、清浄身の人間、虚空身の人間、無憂苦の人間、無量寿の人間、金剛不壊の人間、これが実は吾々人間なのであります。今現在自分の身体だと思っている此の肉体は「念の影の人間」でしかないのであります。如来とは真如から来生したと云う意味で真如から離れて如来はないのであります。 それと同じく真如から放射された観念である人間も真如から放れて存在することはあり得ないのであって真如と人間とは一体なのであります。太陽から放射された光線は太陽とは別な存在ではない、太陽を放れて太陽の光線は存在しない。太陽の光線は太陽とは一体である。それと同じことであります。死ななくとも、死んでも生きても、このまま吾々は如来だと云う真理を体得した境地を修験道では「即身即身」と申しております。 吾々は現在そのままが如来である、如来でないものは一人もない。佛でないものは一人もない。月が大空に明るく照ろうが、雲にかくれて照るまいが月そのものは常に明るいのでありまして、本物の自分(人間の本体)は光明無量、寿命無量で極楽にあり高天原に住んで居るのであって、本有の如来とはこのことを指したのであります。形の出家を説き真も俗も区別せず、あるがまま人間そのままの成仏を期して居るのが修験道なのであります。 「善人尚もて救わる、況や悪人をや」という悪人救済の信仰もあります。路傍に立って人に「罪み人よ」と連呼する信仰もあります。神の怒りを信じて戦々兢々たる信仰者もあります。然し修験道の信仰は吾れ生まれながらにして本有の如来だと云い切る宗教なのであります。修験とは人生そのものの當体をあるがままに正しく究竟することなのであります。所謂「法を見ること」なのです。般若智に即して行住座臥するのが佛であり、その佛の「歩み」が道である。心即是佛、佛即是心、心外無法、佛外無心、佛心即道であります。 平凡、卑近、安易、當然なところに佛道は存するのであるが、その道が仲々見付からぬ。恰も日暮れに空腹をかかえて飯炊のために提灯に火をつけて焚き火の火種子を探し求めた愚か者があったと同じことで脚跟下を照顧すると云うこと、別な言葉で云えば自己没却とか、大死一番とか、解脱とか云うことは頭で考え口で云うことは雑作無いが把握容易なものではない。所謂「唯我独尊」の境地に到達しなくては道はなかなか得られないものでありましょう。さればこそ、即身に法如を証する難行苦行の行法も修行も必要となるのであります。古聖先哲等が苦心して「方便の道」を設け、工夫を凝らして「理解の橋」を架け、そして吾々に遺したのであります。 耳に聞き心に思い身に修して 修験道はざっと申せば、如上述べましたような宗教であると私は思うて居るのであります。 (つづく)
[宗報第十号 昭和二十四年十月一日発行掲載] [宗報第二二三号平成十一年新年号再掲載]
(四)宇宙論
宇宙を本体と姿相と作用の三方面から眺めておる点は真言密教と変わりはない。即ち体、相、用の三点から森羅万像を見るのであります。永久変わらない究竟の本体と、ありのままの姿(相)と、それらの働き(作用)を体大、相大、用大、の三大(要素)とするのでありますが、一切万物は畜生や草木に至るまで皆悉く根本において同一であり互いに共通し融通しそれが全体的に一丸となっておるのが宇宙生命であると見るのであります。 体大とは地水火風空識の六つの要素で、これを六大と申しております。佛も衆生も一切の有情非情、悉く此の六大から成っておるのでありまして、これを名称(地、水、火、風、空、識)、形状(方形、円、三角、半月、団形、円相)、性徳(堅、濕、熱、動、無、無礙、了別)、方角と色(中央金色、北方白色、南方赤色、西方黒色、東方青色、十方衆色)、種子(阿、毘、羅、吽、欠、吽)等いろいろな方面から区別しておるのであります。床堅観に云い盡されてありますが三峯相承法則密記に「大日とは五輪を以て依正となし六大を以て体性となす・・・・・然れば則ち諸尊の総体、衆生の根元なり」と説明されてあります。 相大と云うのは四種の曼荼羅のことであります。曼荼羅とは輪円具足と訳されておりますが、あらゆるものを包括し全体として統一のとれた円満なものを指して云うのでありまして大曼荼羅、三摩耶曼荼羅、法曼荼羅、羯摩曼荼羅の四つであります。 大曼荼羅とは相好のことで慈悲円満な相だとか、これにも種々沢山な相がありましょう。亦色彩でいえば白色が淡白や潔白を示すに対し赤色が情熱や興奮を表す如く清浄無垢とか激情真摯とかを表示することになるのであります。 三摩耶曼荼羅とは持物であります。剣だとか輪宝だとか宝珠だとかによって、その性質、動作、誓願、目的などを知ることができる。例えば不動尊が剣をもっておるので智慧の利剣で悪魔降伏の誓願目的を持っておることを知り、薬師如来が宝珠を持てば、これは薬壷であって病人救済の誓願目的を有つておることを知るが如きであります。 法曼荼羅とは、種子、言語、文字等を指し種子曼荼羅とも呼ばれ潜勢力の意味で事物の頭文字やサインの如く象徴を意味し、これによって本体を指示し本性を指示しその意義をあらわすのであります。阿字は胎蔵大日、鑁字は金剛大日を表すが如きであります。 羯摩曼荼羅とは作業のことで業曼荼羅とも云われ一切の活動や動作を指すものであります。吾々の行住坐臥の作業皆これであります。その本質は同一であって悉く四種曼荼羅の徳相を具備しないものはないのでありますから本体を知り本性を覚り徳相を体顕することによって佛境に到達することが出来るのであります。 用大と云うのは身口意の三密のことであります。身体の動作、行為となって表れる行動が身密であり、言語にあらわれる、すべての表明が語密(口密)であり、内心意中の働きが意密であって、すべての生活行動の源泉はここにあるとされるのであります。吾々の心の働きは勿論、事物理法の運行は大日如来意密のあらわれ、音聲言語は、すべてその語密、物心を包括した動作活動は如来の身密であります。 宇宙一切のものを包括した大日如来の身口意三密の作用、普通の常識的理論では現れてこない三密が実は大日如来の生命であって、この如来の三密と吾々の三密と加持感応し所謂入我々入の境界に入ろうとするのが修験の行法であります。 体相用の三方面から申せば佛も衆生も森羅万象も何れもが同一であればこそ、この範疇に入るのであり而も又要素としての此の三大に包括せられるあらゆるものが関連渉入し参與し合って相離れず円融相●、一体一如の姿なのであって所謂「重々相累無隔別、如々一体不雜乱、彼此横竪輪円足、帝綱瑜伽遍法界」なのであるから「覚悟此分為成仏」の可能と根據があるのであります。 単なる宇宙の要素としての六大、その実相としての四曼、その妙用としての三密と云う理論だけでなく、これをそれぞれ具体的事象を通じ、それに即して三大相即の関係を手近な日常生活に活用し実修実證せんとするところに異彩ある修験道の特色があり将来への嘱望があろうと思われるのであります。 (つづく)
[昭和二十五年一月一日号掲載] [平成十一年十月 二二六号再掲載]
(五)成仏論
修験道では真言密教とは稍や異なった立場に於いて三種成仏を建立しております。 一,即身成仏(肉体即ち大日と覚る)=始覚 即身即佛は本体的に衆生を観察したものであり、即身即身は「即事而眞」の本義に立脚した説であります。 「即身即身の所談は當道不共の極説なり、このところ性得本分の頓機を動ぜずして唯是れ常境無相、常智無縁の内證なり、然れば則ち造次顛沛も則ち無相三身の直体なり、語黙動静も亦是れ無相三密の妙用なり、実に是れ修験即座正覚、常住佛果の源底なり」と説明しております。又人間は病気になると甘味も苦い、病気が治れば本来の甘味も分かってくる、甘いも苦いも異なった二つの性質ではなく本来は一つのものである。煩悩菩提もかくの如く妄念に執着するか諸佛内證の佛智によるかの別に因って凡夫ともなれば聖者ともなる。佛智による者は假令煩悩の中にも菩提を證することが出来るのだと説明しておるのであります。 又「修験の行者は行住坐臥如何に用心すべきや」の質問に答え、 「修験の行者は、自身即ち無作三身の覚体、自心即ち一念法界の内證なり。故に我が色心は本より佛体なり。かくの如く即身自佛の心地に安住する時、自然に悪心を止め善心を生じ自他平等にして差別心あるなし。凡そ総持の一戒、唯慈悲の一念を守るべし。慈悲の一念を全ければ自ら十不善を離れん。然れば則ち行住坐臥の所作皆是れ佛事なり。自身是佛の道理を信知するが故に全く自らの断證を労せずして自ら生死を念ぜず。唯衆生の沈淪を念うて一切所修の行を以て衆生に回向す。 行者は衆生に向かい、諸佛は行者に向かう。故に心と佛と衆生と、この三は差別なし。心とは行者の自心即ち成仏と現ずるなり。佛とは已に諸佛と成るなり。衆生は本来佛なり。この三佛の性質輪円異あることなし。若し自心を知れば即ち佛心を知り、即ち衆生の心を知る。諸佛はこれらを覚りて本覚の心城に住し、衆生は一如に迷うて四生の幻野に迸(ほとばし)る。三界は唯心なり。万法は唯識なり。三心平等なるを知るを大覚と名付く、是れ則ち修験の大要、當道の本懐なり」と答えております。 (つづく)
[昭和二十五年一月一日号掲載] [平成十一年十月 二二六号再掲載]
(六)色心論と生死観
真言密教の如く色(地水火風空)と心(識大)の六大を建立することは前述の如くでありますが、修験道は色心共に阿の一字に摂取し而も阿字は第一命息心法なりと説くのであります。六大は建立しましても終局の到達点は息風に帰するのであります。色心の二大を阿字に摂取する所以は阿字息風を根底として六大を説明するからであります。阿字八箇證義はよくこのことを説明しておるのであります。秘密ロイ(口伝)をぬきにしまして左に掲げますと、 〔阿字八箇證義〕 法性の事 中は空仮中の中を意味し、中の中の字の口は口門を意味し、行首とは行のヘンとツクリの中間に首と云う字を入れて一字とし、これをコンと読んでおります。コンは魂なり気なりと註しております(面授ロイを要します) 第三 阿字本不生の事 第四 有情非情阿字第一命也との事 第五 有情非情内外二養の事 第六 有情非情離土生死の事 第七 入息出息生死の事 第八 父母未生已前の事 以上八箇證義は人間萬物の生死を息風に基づくことを明かしたものであります。又、左に掲げます如く阿字を四重に説いております。 四重阿字の大事 初重 能詮阿字 阿(文字言説等) 常に自心中に於いて、一吽字の聲を観じ、出入命息に随い、身と心とを 吾々人間が思慮分別の生ずるは何故かとならば、それは本具の命息が縮まる時初めて思慮分別が生ずる。吾々の生まれる最初も此の息風から起こり、此身滅するとき又此の息風から退去するのである。故に生(生きる=息入)と云い死(まかる=息退)と云うのである。即ち吾々の生死は共に息風の支配するところで、法界から吾々の身中へ命息が入れば、これ生となり其命息が法界へ帰入すれば、これ死となると説くのであります。峯中正灌頂の時の柱源作法は、これらのことを顯示するのでありますが、柱とは乳木で二本の乳木を飯の上に立て父母二気、出入の命息を表示するのであり、葬式の時、佛供の飯の上に二本の箸を立てるのも此の意味であります。源とは陰陽和合二水の義であって深旨は面授に據らねばなりません。印信口訣の中で次のように説明しております。 『凡そ生死の一大事は六大の中の風大の一大なり。この一大全ければ則ち六大和合す、これを生と云う。この一大欠ければ則ち六大分離す、これを死と云う。生死二法は一心の妙用、有無二道は本覚の眞徳なり。所謂一心とは風息、本覚とは自性六大なり、息の字之を思うべし。故に六大和合の時、假に有情と名付く、これ修生轉變六大なり。六大分離の時本非情と号す、これ本有不轉五大なり、非情の本有法体とは生佛三界を亡くし善悪分別を絶す、このところを三世常住法界体性大日と名づくる也。峯中形儀、床形、床定はこれなり云々』と。左の如く又五箇の証文を掲げております。 五箇証文 玉氏経(玉氏とは瑜祗の省字であります)に曰く 裏書に曰く 吹波奈流 誰走登與(吹けば鳴る、吹かねば鳴らぬ笛竹の聲のあるじは誰れと云うらん)云々。 所生の子を子息と云うのは子は次であって、次息即ち息を次ぐの意であります。命息出入りの義深く味わうべきでありましょう。 次に三有六大の事に就いて説明します。三有とは生有、中有、死有の三有であり六大とは地水火風空識の六大であります。 一,生有六大(修生六大で父母和合の因縁によって造られたところの六大である)地(肉、骨)水(血、泪、唾、汗の類)火(温気)風(命息による挙手動足、閉眼開口等の動作)空(鼻口三穴等の空洞)識(命息により諸種の縁に觸れ善悪正邪の分別をする念々の相) 二,中有六大(中有とは中陰とも云い陰は蘊とも譯され聚衆の義で諸法の假和合を表はす)吾々の身体は色心の假和合であり一期の業力盡くると共に滅亡し同時に次に作った業が未来の果報を受ける。其前相として微細な五蘊を受ける。これを中有と云う。中有の六大と云うのは吾々は法界中有の身心なるが故に又これを自性本具の六大とも云うのであります。中有六大は法界の一気を受得した命息であり此の命息は法界中に遍満せる一気である。故にこれを自性本具の六大とも名付けるのであります。 三,死有六大(法界本有六大で三世常住の六大であります) 三有六大の事に就いて彦山修験秘訣集に次の如く説明しております。 『秘傳に曰く、生有と中有の六大は全く本有六大によって建立す。本有六大を離れては更に生有、中有の六大あることなし。譬えば水波の如く水もと波なし。波には水あり。謂わば水に随縁性あり。故に波は風に随って生ず。修生と中有六大も亦是の如し。縁起の波は迷情所見、縁起の六大は迷情の所見なり。修生(子息)と本有(父母の二念)と全体不二なり。假令ば父母二濁水を誘引せらるれば仁念一気を相續す、本有の六大は假に修生六大を生ず。父母愛執二念によりて男女の相を現す(朱に云う。消奴流於、具沫奈良奴泡登見波、誰加二度世仁、毛廻良無) 本覚舎那眞体に達せんと欲せば、赤白二水當体(生有六大なり)に拘わらず一重(本有)不染位(中有六大)』を心に懸くべきなり。嗚呼末代未練の行者等偏いに仁念の二鑁に執して二鑁の生ずる本源を知らず。凡そ流來生死業とは本有六大の上の影像によるなり。法身金剛位(即身即佛とは本有六大本質に由るなり。譬えば鏡は本より萬象を現ずれども其本質は全く實の影像なし實体を知らざる時は本質を志して影像に依るなり。故に生死流來等に執す。實体を知る時は、本質に契當す。故に影像の衆業皆悉く本質に帰し業縁を引せられず。然れば即ち父母所生六大 轉ぜずして即ち一字鑁字(床堅)の覚位を証す。 若し然れば入峯修行の行者等、一期現生の間、自身即ち毘廬舎那を観じ修生の六大を離散し本有にして三世常住法界体性大日に帰する者なり。 御口説に曰く、波は縁起の故に起滅あり。衆生は縁起の故に起滅あり。 波滅すれば本の水となる。衆生滅すれば法界に帰す。法界は全く本不生、 不可得、不去、不来、無始、無終なり。又曰く、波滅して水に帰す、波を 尋ぬれば体なし。風に随って又生ず。其の波も本波にあらず。仁念に仍て 又生ず。其人本人にあらず。唯これ法界の体性なり。故に因はこれ法界。 縁はこれ法界。因縁所生の法も亦法界云々。 裏書に曰く。秘歌に云う。(焼波灰、埋女波土登奈流物於、於保徒、 加奈志哉、不轉肉身)返事に云う。(焼波灰、埋女波土登奈禮波古會、走禮古會走禮與、不轉肉身)朱に云う。『不轉肉身得無漏法の文は大疏の文なり』云々。 天台の一心三観は心法を的指して空假中の三諦圓融する理を観ずる観法であるが、修験の一身三観は一身上の三観であって所謂一身とは修生の大大依身であり、三観とは佛体、衣服、飲食の三であります。佛体とは床堅。衣服は頭襟鈴懸等。飲食とは柱源であります。衣貝は色法。柱源は心法。 袴と脚絆は地大。袍衣は水大。袈裟は火大。顯襟は空大。柱源は風大を資け、風大は心法であり、衣食は身佛を資くと示されてあります。修験に於いては戒律に肉食妻帯を厳禁せざるやの質問に対しましては他宗に於いては肉食妻帯を不浄となし、これを濫行とすれど斯道にては然らず、濫行は愚痴にして愚痴は不浄の根源である。故に愚痴無明を以て不浄とするが淫欲酒肉を以ては不浄とせず。一切諸法は自性清浄にして垢もなく穢れもなし、邪正一如である。此の自性清浄の理を獲得すること、これが戒行であると主張しておるのであります。 (つづく)
[寺門宗報第十五号昭和二十六年一月一日発行掲載] [寺門宗報第二二八号平成十二年四月 日発行再掲載]
(七)入峯修行について
無洗身の苔のの行といわれる入峯修行は亦峯中修行とも申します。大峯は一乗菩提の顯の道場であると共に金胎両部の密の道場でもあります。一定期間山中に籠もって顯密の行をするのが入峯修行であって大峯は十界修行の道場であると同時に秘密灌頂の道場であります。 この修行に従因至果の行たる順峯(春峯)と従果向因の行たる逆峯(秋峯)と因果不二の行たる順逆不二峯(夏峯=華峯)の三種の修行があります。本来は熊野から大峯に入るのが順峯とせられ大峯から熊野にぬけるのが逆峯とせられて居ったのでありますが、春夏秋冬の季節とも関係なく何時しか順逆併修の形となって今日に至って居るのでありますが現在、山中の宿所が荒れ果てた為めや斯道の衰退と共に傳燈も消え、研修も足りなかった為に従来本當両派共に単なる回峯行に陥って頗る不徹底な入峯になって居ったように想われるのであります。早くから目覚めて復興せられて居ったのは故島津傳道師を大先達とする羽黒修験で非常な苦心を凝らして今日に至って居るのであります。最近に至って當山派や彦山派なども復興の計画中であるやに傳聞しております。 形式に於いても作法に於いても名目に於いても本山、當山、羽黒、彦山等いろいろ差異はあるが精神的内容に於いては大体差異は無いようであります。古来各派とも、春峯よりも秋峯に重点を置き最極の修行として居るのであります。峯に入ることをば入成とも駈入とも申し母胎に生を托する密意にたとえて居るのであって、峯中の修行は胎内五位の修行でありますから所謂鉾の滴り島となると云う三牙の式や三獻の式など密行も行われ一ヶ月目から九ヶ月目迄の修行を果たし佛果を得て娑婆世界に還生するにたとえ出峯を出生=出成、或いは駈出と呼ぶ修行でありますから古来親兄弟、師弟、同朋の間と雖も他言厳禁の修行であり口傳口訣も多く大先達直授の密行であって勿論紙上にに顯露出来ないのであります。従って概略の記述に止むめるのやむなき次第であります。順序は駈入から始まって一宿から三宿まで道場を履修するのでありますが宿の入口出口には結界安鎮のために小柴と称するものを立てる、これは山門に仁王尊を安置すると同意義のもので本山派に於いては執金剛であるとし羽黒では除魔童子、金剛童子の二童子であるとして居ります。 行者は入峰前三七日精進潔斎し初夜後夜、日中の三時の勤行を勤め新客、度衆は入峯の前日、正先達の室に集まり長床左右の席次を定めるのであります。床とは両界の曼荼羅十界凡聖同居の道場を云うのであってアビラウンケンの堅固法身の五大たる自身即佛の形儀をバン字の形に堅(ツム)るのが長床と云うのであります。これと同時に五人の先達が定まるのであります。峯中先達(正先達)=中央大日。小木先達=東方阿●。柴燈先達=南方寶生。宿先達=西方彌陀。閼伽先達=北方釈迦。の五先達は先達柱に座する正先達の前方両側に座し、度衆新客は年臈度位に依って正先達に向かって二列に座し(宿中の床もこの形で勤行する)手碑傳草案、現参帖、床帖を始め縁笈、肩箱等の諸道具を用意するのであります。 入峯行列の次第は斧、法螺、手碑傳、縁笈、小木、柴燈、正先達、宿、 閼伽、閼伽桶、度衆、新客と順序するのであるが大峯派は右手に檜杖や金剛杖や擔木を持つのであるが、羽黒派は左は自行、右は化把とする口訣によって左手に持つと云った差異があります。 宿に着けば入宿の儀を行う。先ず入宿の螺を立つ。逆行道三反。柴燈先達は小木を指南して庭柴燈を焼く。宿中に於いて正先達は閼伽と小木の文を授け法儀を行う。これは汲水採薪の苦行を儀禮化した行法であります。 それから固打木の作法もある。初夜の勤行もする。入宿灌頂もある。度衆新客は訓戒や誓約を受ける。禮拝もさせられるのであります。 入峯中新客が順次に行う行法として十界修行がある。十界の各界に十種の行がそれぞれ配當せられて居り、且つそれは峯中の日程と行場とにも配當せられて居るのであるが、その次第は順峯と逆峯によって異なるのであります。然し便宜的に行われて従来一定しては居らぬようであります。 十界修行を、ここでは三十三通記や修練秘要義の説に據って左記すれば (一)地獄ー業秤 (二)餓鬼ー穀断 以上の十界修行は次回から解説するつもりでありますが、峯中にはいろいろの密行があり又異名も多いのであります。四五の例を挙げますと反閇(へんばい)と云うことがある。これは採灯護摩の場合にも現れるのであります。結界安鎮と瀉浄と鎮魂との混融した忍辱の行たる固打木の作法がある。大懺悔の行もある。施餓鬼の行もある。三關三渡と云うことや鍵向門、五穀両壇都率内院、四門の行とか蛭兒、素盞鳴尊。日神、月神。即身即佛を見奉ること。不動灌頂とか、地獄嶽のことや玉木のこと、番渡し、阿弥陀嶽のこと或いは子守勝手の行とか、金掛け西のぞき一体の行とか、泥川の行事、節の行事、阿古瀧のことや、神通寺瀧の行事とかイナムラ嶽の行事とか笈渡しとか深秘のものがいろいろあるのであります。又食事のことを御散杖又は行事と云ったり、番を仁王、素麺をイトヨリ又は般若と云ったり、香の物を小佛、大根を白根、牛蒡を黒根、沢庵漬を大金剛、蕨を古クギ、豆腐を御幣、餅を赤金の御正体、白金の御正体などと申して居ります。 又入峯修験十六道具としては頭襟(一頭)班蓋(一蓋)結袈裟(一領又は一帖)鈴懸(一具)法螺(一面)錫杖(一振又は一本)念珠(一連)金剛杖(一本)書笈(一丁又は一絡)形箱(一合)引敷(一疋又は一枚)脚絆(一足)柴打(一振)又は螺緒(一腰又は一口)走縄(一筋)檜扇(一本)草鞋(一足)であって、是非なくてはならぬ用具とせられて居ります。これに一,二異説もあります。 (つづく)
[寺門宗報第十六号昭和二十六年五月一日発行掲載]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||