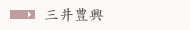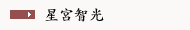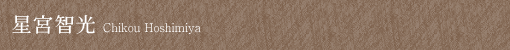三帰依文
一 仏教がもっとも大切な宝としているものに、仏宝と法宝と僧宝があります。これを三宝といいますが、この三宝に帰依することは、仏教者であることの欠くべからざる必要条件でもあるわけです。「帰依三宝」は、釈尊いらい今日まで、そしてどんな社会においても仏教者の普遍的な、そして絶対に必要な心のありかたであります。仏教はここにはじまって、ここでおわるといっても過言ではないと思います。 二 帰依三宝は、ふつう「三帰依文」といわれることばに表現されてあります。 われ仏に帰依したてまつる ということばにまとめられてあります。これを天台宗では、次のようなことばで勤行のはじめに太文字の部分を唱えることになっております。 三帰依文(さんきえもん) 人身受けがたし、今すでに受く 仏法聞きがたし、今すでに聞く この身、今生に度せずんば さらにいずれの生においてか、この身を度せん 大衆もろともに至心に三宝に帰依したてまつる。 みずから仏に帰依したてまつる まさに願はくは衆生とともに 大道を体解して無上意を発さん みずから法に帰依したてまつる まさに願はくは衆生とともに 深く経蔵に入りて智慧海のごとくならん みずから僧に帰依したてまつる まさに願はくは衆生とともに 大衆を統理して一切無礙ならん 三 もし毎朝の出勤でどうしても長い時間の勤行がとれないようなときは、ただこの短文の三帰依文(太字部分)を仏壇の前で唱えれば十分であるといえます。もちろん、ねんごろに如法の勤行はこのましいことですが、もし事情があって、ねんごろな勤行をつとめかねるときは、この三帰依文を心をこめてなすことがよいと思われます。しかし、心をこめることが大切なのはいうまでもありません。ふつうは、この三帰依文の告白は、五体投地による頂礼によって行われます。五体投地とは、額と両手両足のひじを地面に付けてする、もっとも信順の心をあらわす礼拝の仕方です。すなわち、心の底からの信順帰依を仏法僧の三宝にささげる。これが仏教者の生活の第一条件であるわけです。
懺悔
どのような宗教でも、自分の無力を自覚することから始まるといってよいでしょう。仏教の出発点も、自分の無常、人生の苦を自覚することにあり、そこからの解脱が最終の目的となるわけです。自分の無力無常の自覚というのは、また自分の罪障への反省ということにもなります。わたしたちは仏の救いの手を求めるのでしょうか。自分の罪障(ぼん悩)を乗りこえ、安心立命をうるためです。そこで、わたしたちは仏の前に立ったならば、まず全身全霊をもって自分の罪障を悔いることをいたします。まず、自分の罪を認めなければなりません。そして、それを仏の前で仏の助けをかりながら懺悔するのです。どんな場合でも、勤行のとき、最初に次のような「懺悔の文」を心から血涙をふりしぼって唱えます。 我、昔より造りしところの諸々の悪業は 皆、無始からの貪と瞋と癡による 身と口と意より生ずるところなり 一切をわれ今みな懺悔したてまつる この文は、「略懺悔」ともよばれ、『普賢観経』のなかの偈であり、天台宗だけでなく、各宗派が用いています。懺悔は、仏教の修行の重要な一つになっております。みずから意識するしないにかかわらず、自分が犯したであろう罪過を全身全霊をもって悔い改め、仏の前に全てを告白発露し、そのゆるしをえて、心身を清浄にするわけです。懺悔はさとりであるといわれるほどに重要な、仏教者のおつとめの一つです。懺悔によって、われわれは仏の前で、罪悪深重の凡夫から清浄な菩薩に生まれかわるのです。 天台宗で毎日つとめねばならない勤行に「法華懺法」がありますが、これは『法華経』に出ているあらゆる三宝(仏法僧)の前で、自分の罪業を悔いる勤行です。したがって、「法華懺法」では、懺悔、勧請、随喜、回向、発願などの部分から成り立っておりますが、その中心はやはり懺悔です。その部分で唱えることばは、つぎのようなものです。 至心に無量の罪を懺悔したてまつる 我および法界の諸の衆生、無明 四重五逆等、ないし謗法の罪を造作し みずから作し他をして作さしめ、作すを見て随喜せり。 我等、いま諸仏の前にたいして衆多の極重罪を発露し 至心に慚愧しことごとく懺悔したてまつる 仰ぎ願はくは、十方一切の仏、すでに作れる罪はことごとく消滅し、未来の悪をしてさらに造らざらしめんことを。 懺悔しおはりて、三宝に礼す 仏教の修行はいろいろありますが、懺悔がなければはじまりません。というより、仏教修行は懺悔にはじまり、これにおわるというべきかもしれません。自分の意識しないで犯した過ち、意識して犯した罪、すべてを全身全霊をもって仏の前に悔いることによって、わたしたちは真の仏教者として生まれかわることができるのです。
十如是と円頓章
朝夕の勤行のときに読誦する経文や真言は、いずれも天台の教えと信仰を簡潔にのべております。そこで、それらのなかから、とくに教養的に重要なものを取りあげて解説してみます。 はじめに「十如是」の句ですが、これは鳩摩羅什という中国僧が漢文に翻訳した『法華経』の方便品のなかの文から抜き出したものです。天台大師の教義は諸法実相(すべての存在するものはそのまま真実である)という思想であるといわれますが、それはさらにくわしく空と仮と中の三諦が円融して一つであるとも説明されます。そして、その解釈は方便品の十如是の文句を通して成立するといわれます。つまり十如是の句は、天台の教えのもっとも中心点をのべているということになります。そこで、古来から経文と同様に重視し、天台宗徒は、読誦しているわけです。 〈十如是〉の句の和訳 仏の成就したまえる所は、第一稀有難解の法なり。ただ仏と仏とのみ、いましよく諸法実相を究尽したまふ。いわゆる諸法の如是の相、如是の性、如是の体、如是の力、如是の作、如是の因、如是の縁、如是の果、如是報、如是の本末究竟等なり 解釈 仏のなしとげられた悟りは、最高でかけがえのない完全なもので、だれにでも理解できるというようなものではない。 仏と仏とだけがはじめて諸法は実相であるという難解な真理を実によく究めつくすことができたのである。 それはいわゆるあらゆる生存と現象の存在における如是の相(相はそれぞれ存在するものの表面的なすがたを意味する)、如是の性(性は内面的な習性)、如是の体(本体)、如是の力(力は潜在能力)、如是の作(作用)、如是の因(直接原因)、如是の縁(間接原因)、如是の果(因縁による結果)、如是の報(結果が現実になったもの)であり、如是の本末究竟等(本末究竟等とは、前の九つがたがいに一貰していること)である。すなわち、あらゆる存在するものを相から報にいたる面から追求しても、それぞれ特性をもつ存在が区別のまま存在意義をもち、しかもそれらは固有性をもちつつ互いに円融しあって無差別平等の境界に通じているものである。 ついで〈円頓章〉が重要である。この文章は「円頓者・・・・」ではじまるので、円頓者ともよばれます。天台の仏道修行の仕方をくわしく論じた『摩訶止観』という本の序文のなかの文句を抜き出したものです。この序文は『摩訶止観』を天台大師が口述したとき、これを筆録して十巻の書物に整理した弟子の章安尊者が、天台止観の真髄をまとめたものです。ただし、最後の六句は第六祖の渓荊尊者の文で、『摩訶止観輔行伝弘決』のなかで天台大師の一念三千を説明しているところに出ているものです。円頓章の文章が天台大師の悟りの究極を表現している一念三千と同じ意味であるということから、この六句が終末につけくわえられているのです。 この円頓章には、天台教学の中心思想がすべて含まれており、たいへん難解な文章ですが、それだけにしっかりと理解するようつとめたいと思います。 〈円頓章〉の訳文 (1)円頓とは初めより実相を縁ず、境にいたるに即ち中にして真実ならざること無し。 (2)縁を法界に繋(か)け、念を法界に一(もっぱ)らにす。一色も一香も中道に非ざること無し。己界および仏界・衆生界もまた然り。 (3)陰入みな如くなれば苦の捨つべき無く、無明塵労すなわちこれ菩薩なれば集として断ずべき無く、 (4)辺邪みな中正なれば道の修すべき無く、 (5)生死すなわち涅槃なれば滅として証すべき無し。苦無く集無きがゆえに世間無く、道無 く滅無きがゆえに出世間無し。 (6)純(もっぱ)ら一実相にして、実相の外にさらに別法なし。法性寂然なるを止と名づけ、寂にして而も常に照らすを観と名づく。 (7)言ふこと初後なりといえども二無く、別無し。これを円頓止観と名づく。 (8)当に知るべし、身上は一念三千なり。ゆえに道を成ずるのとき、この本理に称(かな)い、一身一念、法界に遍(あま)ねからん。 〈解釈〉 (1)円頓というのは、仏教の初心から、生きているありのままのすがたが、真実と縁起という関係において存在していることを、仏教的認識によって自らのものとする観法修行をしていくことである。真実を認識し理解するための対象は空であって、絶対的存在はないとされるから、あらゆるものは仮の存在であると把えられ、空にも仮にも執われない中道ということになり、このような意味であらゆる生存や現象の外に真実というものはなく、あらゆる存在がそのまますべて真実でないものはないとさとるのである。つまり初発心においてただちに究竟の真実在に到着しているということを円頓というのである。 (2)あらゆる存在や現象も相依相関の縁起によって存在しているから、わが一念つまり一瞬一瞬のいまの心がそのまますべての世界に連なっているのである。だから、たとい一枝の花も一つまみの香も、どの存在を一つとってみても、それらはすべて中道真実にかなっていないものはない。こうして、自己の世界も仏のさとりの世界も、生あるあらゆるものの世界も、同じく真実にかなっていて、まったく別のものではない。 (3)釈尊は人生は苦であると苦諦を説かれたが、人間存在を成立たせている要素である五蘊はみな真如であるから、苦も苦であるからといって捨てさるべきではない。同じく集諦についても、生と死に流転している根本原因といわれる無明や、迷いや執われの煩悩は、煩悩すなわち菩提と観法する円頓の境地からいえば、苦の原因である世界の無常と人間の執着も除き去るべきものではない。 (4)さとりに到るための道諦についてもかたよった二辺に執われ、善行に反するよこしまな思想や行いもそのまま中道であり正であると観法するときは、とりたてて修行ということに執われることもない。 (5)仏教の終局の目的の涅槃である道諦についてもまた同様に生と死に流転する人生そのままが、生死すなわち涅槃であると観法すれば、修行によって涅槃のさとりを証するということもなくなる。 (6)ただもっぱら有るがままの生存だけが現実なのであって、この迷いのままのすがたの外に、別の世界としてのさとりの法があるわけではない。あらゆる存在の本体である真理は、寂然不動なるものであり、これと一体である己れの心も寂然そのものであり、こういう側面を〈止〉と名づけ、この真理性が法性として寂然不動のまま同時にはたらきをもつ側面を〈観〉というのである。 (7)このように初発心とか修行中とか表現されるが、円頓の絶待妙からいうならば、二つあるわけでなく、また別のものであるわけではないのであって、このような思考と実践が円頓止観というのである。 (8)だからこそ知るべきであろう。この衆生世間と、その住所である国土世間と、それらを成り立たせている五蘊世界は、三千の数によって表現された一切すべての世界にあまねく具現しているのである。さとりを得たとき、この一念三千の理にかなって、わが身体もわが心もあらゆる存在が仏法であり、あまねく世界に遍満していることが体得されるのである。
自我偈
一 天台寺門宗では、法華経と大日経の二つの経典をもっとも大切なものとしております。 そこで、今回は、本門の中心の中心、すなわち法華経の中心である寿量品の、ふつう「自我偈」とよんでいる詩文の和文とその説明をしてみます。 二 仏とはいかなるお方であるか。これにはいろいろの答があります。まず仏とはわたしたちと同じく人間と生まれ出家苦行の後にさとりをひらかれ、一代の間、説法教化して終に涅槃に入られた釈迦牟尼世尊であるというでしょう(応身仏)。また仏とは量りもない遠い昔にすでにさとりをひらいて無量の光明を放ち無量の寿命を保って、いま現に極楽浄土にいる阿弥陀如来であるというでしょう(報身仏)。また仏とはこの世のあるがままの理(ことわり)、あるがままのすがた、すなわち「法」そのものであって色も形もない、しかしあらゆる世界に満ちて滅びることのない真理そのものを名付けたというでしょう。(法身仏)。このように仏はいろんな見方ができ、これを仏の三身といいます。 ところで釈迦牟尼世尊は老境に入られて、自分の入滅をその弟子達にあらかじめ告げるとともに、はじめて仏はこの世に始めて仏となったのではない、久遠の昔よりすでに仏となって、つねに説法し生もなく、また滅もなく、永くこの世に住まってつねに衆生を教化したまうと説かれました。これが法華経如来寿量品であり、それを要約して詩文にしたものが自我偈であります。したがって自我偈こそは実に一代仏教の眼目というべきものです。 なぜ、これを自我偈というかというと、それはこの詩文の冒頭が「自我得仏来」という言葉ではじまるからです。 三 (本文) (意訳) (本文) (意訳) (本文) (意訳) そこでわれすなわち釈尊が、多くの衆生をみるにみな苦の海に沈んでいる。いかにも哀れであるから、それらの衆生をして如来にたいする渇仰の心を生ぜしめんがために、しばらく身を隠す。これを衆生は実に涅槃に入られた、滅度されたと考えるのである。しかし衆生が一心にお会いしたいと渇仰し、恋い慕う時にはすなわち出でて法を説くのである。如来は、このように常住に滅せざる力であり用であるが、ただ神通力をもって、あるいは身を現わし、あるいは身を隠すのである。しかし、いかなる時でもつねに霊鷲山および余の一切の住所にあるのである。 (本文) (意訳) このように世の中をみるというのは、衆生の悪業の因縁によるところであって、かれらにあっては無数劫の長年月を過ぐとも、仏の名さえ聞くことができない。すでに三宝の名を聞けないというのであるから、仏身をみるということはもちろん不可能である。これに反して、正直な者は釈尊が霊鷲山にありて説法教化するのをみることができる。このすぐれた浄土の仏をみることのできるのは位の高い菩薩であって、それらにたいして仏は、仏の寿命は無量であると説き給うのである。そこで、経には、ある時はこの衆のために仏の生命は無量なりと説き、あるいは末法悪世の邪見の衆生であっても、ながくよい行いを修行して後でなければ仏をみたてまつることのできない者にたいしては、ために仏には値いがたしと説かれたのである。菩薩には真実を説き、衆生には方便の説法をされるように、仏の智慧は自由自在である。それゆえに「わが智力かくのごとし、慧光照らすこと無量にして、寿命無数劫である。これは久しく善悪を修して得るところである。汝等智恵ある者は久遠実成の仏身において疑いを生じてはいけない。その疑いはながく断じつくさなければならない。仏ののべるところは一切みな真実であって、いささかも嘘偽りはないのである。たとえば、よい医者が方便をもって子どもの病気を治したとする、その方便をだれもうそとはいわないであろう。われもまた名医がその子の病気を治したごとく、世間の父となって、衆生の苦しみを救うものである。 (本文) (意訳)
法華経普門品(観音経)の偈文
法華経の観世音菩薩普門品(第二十五)の偈文が、いわゆる「世尊偈」であります。この普門品は一つの経として特別に取り出されているほどに一般に信奉されている章であります。 観世音菩薩とはあまねく世を照らし見、世のさまに応じて救いの手をさしのべることを、人格的に表現したものでありあす。観世音菩薩の名を唱えることによって、火難、水難、羅刹(食人鬼)難、刀杖難、鬼難、枷鎖(束縛)難、怨賊難の七難が消滅すると説いています。またむさぼり(貧欲)、いかり(瞋恚)、おろか(愚痴)の三毒を除き、男の子を生みたいと思うならば男の子を、女の子を望むなら女の子が授かるとものべております。 また、観音菩薩は人びとの望みや能力機根に対応して三十三身に変現して、救済につとめるとも説かれています。これは観世音菩薩の慈悲の無限なことを象徴しているものであります。つまり「是の菩薩はよく無畏をもって衆生に施す」とあるように、観音菩薩は施無畏者として人びとから恐怖や不安をとりのぞく者のことで、これは信仰を支えとして人生を恐れることなく歩むよう、つよく励ますところに、普門品のねらいがあるので、これを美しい詩文の形にまとめたものが、わたしたちの親しんでいる「世尊偈」であります。 つぎに、「世尊偈」を和文にし、これに注をつけ説明してみます。 世尊は妙相を具したまへり、 「汝よ、観音の行の善く諸の方所に応ずるを聴け」 われ汝がために略して説かん 仮使、害う意を興して あるいは巨海に漂流して 神通力を具足し 種々の諸の悪趣と 真の観、清浄の観 悲の体たる戒は雷の震うが如く 諍訟して官処を経て 妙なる音、世を観ずる音 その時、持地菩薩は、即ち座より起ちて、前みて仏に白して言わさく「世尊よ、若し衆生の、この観世音菩薩品の自在の業たる普門示現の神通力を聞く者あらば、当に知るべし、この人の功徳は少なからざることを。」と。 仏、この普門品を説きたもう時、衆中の八万四千の衆生は、みな無等々の阿耨多羅三○三菩薩の心を発せり。 要するに、この普門品は、寿量品において開顕された久遠の本仏が大悲により、われわれと直接関係の深い娑婆世界に観世音菩薩として現れて、危難の衆生を自由自在に救済することをのべたものであります。かの観音の力を念ずるならば、ありとあらゆる苦難から救われるのであり、そのことから法華経への帰依をすすめているのです。これを要約して美しい詩歌の形をとって賛嘆したもの(頌)が「世尊偈」であり、これを日々に読誦することは万難を除き福寿を招くことにほかならないわけです。 古来、中国をはじめ東南アジア、日本を通じて、この観音信仰が広く一般社会に盛んに行われてきたのは、こうした観音菩薩の広大無辺の慈悲と救済に帰依してのことであります。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||